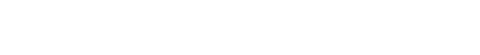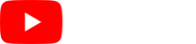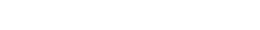ニュース
漆喰塗料で、手の届く「理想の空間づくり」を
コラム / 2025.06.23
自分の手で空間をつくるという選択
DIYで「理想の空間」を形にしたい人が増えている
自分の暮らす場所を、自分の手でつくる——。
そんな選択肢が、じわじわと広がってきています。
たとえば、長年空き家だった古民家を再生して、週末のセカンドハウスに。
あるいは、使われなくなった古い物件を借りて、自分好みのカフェやギャラリーを立ち上げる。
こうした「空間の再編集」に魅力を感じ、プロに任せきりにせず、
自ら手を動かしてリノベーションに関わる人たちが増えてきました。
理由はいろいろあります。
コストを抑えたいから、という人もいるでしょう。
でも実際はそれ以上に、「自分でつくること」そのものに価値を見出す人が多い。
自分で塗った壁、自分で選んだ色、自分で作った棚。
その空間には、ひとつひとつに思い入れが宿ります。
完璧な仕上がりじゃなくてもいい。むしろ、多少のムラやズレこそが、
「ここは自分の場所だ」と思える愛着を育ててくれるのかもしれません。
そうした背景もあって、「DIY=安く済ませる手段」だったものが、
今では「自分の感性を形にする方法」として再評価されています。
理想の空間は、誰かが用意してくれるものではなく、自分で選び取り、つくりあげていくもの。
そんな意識の広がりが、漆喰塗料のような“素材”への関心を高めています。
漆喰の壁が持つ、独特の温もりと存在感
「塗るだけで、空間の空気が変わる」
そんな体験ができるのが、漆喰の壁です。
漆喰は、石灰を主成分とした自然素材。日本では古くから城や蔵、
住宅の内外装に使われてきた伝統的な左官材です。
その魅力は、見た目の美しさだけではありません。
漆喰は呼吸します。
湿度が高いときには水分を吸い、乾燥しているときには吐き出す。
空間の湿度を穏やかに調整してくれるため、壁がただの“仕切り”ではなく、空気の質をつくる一部になってくれるのです。
また、漆喰のもつアルカリ性には、カビや雑菌の発生を抑える性質もあり、
清潔で快適な空間を保ちやすくなるというメリットもあります。
でも何より魅力的なのは、やはりその“表情”でしょう。
光をやわらかく受け止め、陰影の出る独特のマットな質感。
塗った人の手の動きがそのまま模様となって現れる、唯一無二の表面。
機械的に均一なクロスやペンキとは違い、漆喰の壁は空間に静かな個性を与えてくれます。
とはいえ、本格的な漆喰を塗るには、左官の知識や技術、道具が必要です。
ハードルは決して低くありません。
そのなかで近年注目されているのが、「漆喰塗料」という選択肢。
見た目や質感は漆喰のように自然で美しいのに、扱い方は“塗料”としてシンプル。
コテではなく刷毛やローラーで塗れるものも多く、DIY初心者でも挑戦しやすくなっています。
漆喰塗料は、伝統と現代の“ちょうどいい間”にある素材。
自分の手で理想の空間をつくりたい人にとって、とても頼もしい味方になってくれるはずです。
漆喰塗料って何?——素材としての魅力と可能性
漆喰と漆喰“風”塗料の違い
漆喰。
それは数百年にわたって、日本の建築文化を支えてきた左官材です。
白壁の蔵や、寺社の塀、伝統的な日本家屋の内壁などに使われてきたその姿は、
私たちの記憶の中に“落ち着いた美しさ”として刻まれています。
本物の漆喰は、消石灰を主成分に、麻すさ(繊維)や海藻糊などの天然素材を練り合わせたもの。
職人の手で丁寧に塗られ、乾燥し、硬化していくことで、何十年もの時を超えて空間を守ってきました。
しかし、その施工には高度な左官技術が求められます。
コテを自在に操る熟練の手、何層にも渡る塗り重ね、乾燥の見極め…。
「美しいけど、自分には無理」と思ってしまうのも、無理はありません。
そこで登場したのが、「漆喰塗料」というアプローチ。
本物の漆喰のような風合いを持ちつつ、よりシンプルな手順で施工できるように設計された塗料です。
一部の製品には、石灰や天然素材を含むものもありますが、基本的には“扱いやすさ”が第一優先。
コテではなく刷毛やローラーで塗れることが最大の特徴です。
仕上がりの雰囲気は製品によってさまざまですが、「自分の手で空間を変える」ことを
目指す人にとって、大きな味方になってくれる存在です。
つまり、漆喰塗料とは、“漆喰の代用品”ではなく、自分らしい暮らしを手に入れるための、現代的な選択肢の一つなのです。
漆喰塗料のメリット・デメリット
漆喰塗料の魅力は、単なる「手軽さ」だけではありません。
実際にどんな特徴があるのか、メリットとデメリットの両面から見てみましょう。
🟢メリット
-
施工が簡単で、道具も少ない
左官用のコテや専用の下地材を使わなくてもOK。刷毛、ローラー、マスキングテープ、養生シートなど、ホームセンターで手に入る道具で始められます。
-
初心者でも仕上がる安心感
コツは必要ですが、コテ跡の妙技や材料の練り具合に悩む必要はありません。
マニュアル通りに進めることで、十分美しい仕上がりになります。
-
独特の質感が得られる
製品によっては、マットな表面や、ざらっとした手触り、光の陰影がやさしく映る表情を
再現可能。白一色でも深みのある空間に仕上がります。
-
環境・健康への配慮
VOC(揮発性有機化合物)を含まない製品や、天然素材由来のものもあり、
小さなお子さんやペットがいる家庭でも安心して使えます。
-
手頃な価格で空間の印象を変えられる
壁一面を変えるだけでも、空間の雰囲気はガラリと変化。
家具や床を変えずに“模様替え”できるのは、コスト面でも大きな魅力。
🔴デメリット
-
本漆喰と全く同じものではありません
調湿・消臭・耐久性などの性能は、やはり本物の漆喰と全く一緒ではありません。「見た目が近いが、構造は違う」点は認識が必要です。
-
製品によって仕上がりにバラつきがある
中には、“ただの白い水性塗料”のように感じるものもあり、漆喰らしさが出にくいことも。
選ぶ際は、テクスチャ見本やレビュー確認が重要です。
-
施工面積や塗布回数でコスパが左右される
1回塗りで済む場合もあれば、2度塗り以上必要な製品もあります。
製品説明の確認と、面積の見積もりは丁寧に。
漆喰塗料は、本漆喰に比べて“完璧”ではありません。
でもその分、「自分でもできる」という強さがあります。
DIYにとって最大の障壁は“技術”ではなく、“自分にもできると思えるかどうか”です。
もしあなたが、これまで「DIYなんて無理」と感じていたなら、漆喰塗料は
そのハードルをそっと下げてくれる存在になるかもしれません。
そして、もし選ぶなら、次のセクションで紹介する「CALMUR(カルミュール)」のような、
“はじめの一歩に最適な一缶”と出会えると、なお心強いはずです。
DIY初心者でも安心!塗装の基礎知識
「漆喰塗料が魅力的なのはわかった。でも、やっぱりDIYって難しそう…」
そんなふうに思っている人にこそ知ってほしいのが、この「塗装の基礎知識」です。
DIYは、特別なスキルやセンスがないとできない——そう思われがちですが、実際は
「正しい準備」と「基本的な工程」さえ押さえれば、初心者でもきれいに仕上げることができる作業です。
ここでは、初めての塗装でも安心して始められるように、基本中の基本をまとめてみました。
塗料の種類と特徴
まずは、塗料そのものについて。
ホームセンターや通販サイトを見ると、驚くほど多くの種類が並んでいます。
漆喰塗料を選ぶ際にも、ベースとなる塗料の知識があると、迷いが減ります。
● 水性塗料 vs 油性塗料
-
水性塗料:扱いやすく、匂いも少ない。屋内DIY向け。
-
油性塗料:耐久性が高く、屋外や水まわりに向いているが、扱いに注意が必要。
漆喰塗料は、基本的に水性塗料ベースで作られているものが多く、初心者にも扱いやすい仕様になっています。
● 仕上がりの質感
-
マット(つや消し)タイプ:落ち着いた雰囲気。漆喰塗料はこの質感に近い。
-
つやありタイプ:光沢があり、汚れが拭き取りやすいが、漆喰の風合いとは遠ざかる。
● 色の選び方
漆喰=白、のイメージが強いですが、漆喰塗料にはやわらかなグレー、ベージュ、
くすみカラーなど、空間になじむ色味も多くあります。
「白すぎると浮くかも?」と不安な方には、少しトーンを落とした色もおすすめです。
必要な道具と準備
DIY塗装を成功させるかどうかは、8割が「準備で決まる」といっても過言ではありません。
ここでは、最低限必要な道具をリストアップします。
🧰 基本の道具
-
塗料(漆喰塗料)
-
刷毛 or ローラー
-
トレイ(塗料を入れて使う)
-
マスキングテープ
-
養生シート or 新聞紙
-
布 or 雑巾(拭き取り用)
-
やすり(必要に応じて下地処理)
-
混ぜ棒(塗料を均一にする)
道具は、100円ショップやホームセンターで手軽に揃えられます。
DIYキットとしてまとめられている製品を選ぶのもアリです。
🧼 養生は“やりすぎ”くらいでちょうどいい
壁を塗る前に行う「養生(ようじょう)」は、塗らない部分を保護するための大事な作業です。
マスキングテープをまっすぐ貼るだけでも、仕上がりの美しさが大きく変わります。
「ちょっと面倒だな」と感じる人も多い工程ですが、ここを丁寧にやることでDIY感が消え、プロっぽい仕上がりになります。
失敗しないためのコツと注意点
▶ 1. 試し塗りは必須
いきなり本番の壁に塗らず、段ボールや紙などに試し塗りをして、質感・色・塗り心地を確認しましょう。
CALMUR(カルミュール)のような製品は、テクスチャによって見た目が変わることもあるので、事前チェックは必須です。
▶ 2. 一気に塗りきろうとしない
「集中して今日中に終わらせたい!」と頑張りすぎると、塗りムラができたり、乾く前に重ね塗りしてしまったり…
というトラブルが起こりがち。小さな面積から始め、余裕を持った時間設定がおすすめ。
▶ 3. 乾燥時間は守る
塗料にはそれぞれ「乾燥時間」があります。焦って次の工程に進むと、下の層が乾かず、
仕上がりに影響が出ることも。製品に記載された目安時間は必ずチェックしましょう。
▶ 4. 塗り始めは“目立たない場所”から
最初はうまく塗れなくても当然。いきなり部屋の真ん中から塗り始めず、
目立ちにくい壁の端や、家具で隠れる部分から始めるのが安心です。
「初めてだからこそ、丁寧に準備して、無理なく少しずつ」が成功のカギ。
漆喰塗料は、道具もシンプルで扱いやすいので、塗装初心者の“初チャレンジ”にぴったりの素材です。
次のパートでは、そんなDIYデビューにぴったりの製品「CALMUR(カルミュール)」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
CALMUR(カルミュール)とは?
「漆喰のような質感のある壁を、自分でつくってみたい」
そう思ったときに頼れる選択肢が、CALMUR(カルミュール)です。
CALMUR(カルミュール)は、漆喰のようなナチュラルな質感と、塗料ならではの扱いやすさを兼ね備えた水性の内装用塗料。
DIY初心者でも取り入れやすく、なおかつ空間の印象をぐっと引き上げてくれる
——そんな“ちょうどよさ”を目指して開発された、新しいタイプの漆喰塗料です。
CALMURの特長と、他製品との違い
漆喰塗料と一口に言っても、その性質や仕上がりは製品ごとに大きく異なります。
CALMUR(カルミュール)の大きな特長は、以下の3点です。
① “塗った感”のない、自然な仕上がり
CALMUR(カルミュール)の塗膜はマットで、光をやわらかく拡散させる効果があります。
照明の角度や時間帯によって、壁の表情が少しずつ変わるような繊細さがあり、単なる「白い壁」にとどまりません。
まさに「空間に呼吸を与える」ような仕上がりです。
また、表面はほんの少しだけざらつきがあり、手で触れても気持ちよい質感。
見た目だけでなく、触れたときの心地よさまで設計された塗料です。
② ローラー施工でもムラになりにくい
DIYでありがちな悩みのひとつが「塗りムラ」ですが、CALMUR(カルミュール)はローラーで塗っても
塗料が均一に広がりやすく、初心者でも扱いやすい設計になっています。
「塗ったときはムラに見えたけど、乾いたら落ち着いた質感に仕上がった」という声も多く、
安心して使える製品として高く評価されています。
③ カラーバリエーションが絶妙
漆喰というと“真っ白”なイメージがありますが、CALMUR(カルミュール)は
くすみ感のある落ち着いたトーンのカラーラインナップもご用意しています。
白だけでなく、ライムストーン、フレンチバニラといった、照明の光や家具になじむ色味が揃っています。
どの色を選んでも「主張しすぎず、でも空間の印象はしっかり変わる」——そんなバランスがとれています。
なぜ初心者にも扱いやすいのか?
CALMUR(カルミュール)は、“DIYのはじめの一歩”を想定して作られているからこそ、細かなところにも配慮が詰まっています。
-
ローラー・刷毛での塗装に対応(コテ不要)
-
高粘度すぎず、垂れにくい設計
-
乾燥時間が短く、塗り重ねもスムーズ
-
臭いが少なく、室内作業でも快適
このように、初めての塗装でもストレスが少ないように工夫されているため、作業中も後も気持ちよく進められます。
また、下塗り材や、推奨される道具類が明示されている点も初心者には嬉しいポイント。
何を揃えたらいいかわからず戸惑う……という“最初の壁”をしっかりケアしてくれます。
CALMUR(カルミュール)が向いているシーン・空間とは
CALMUR(カルミュール)は、その仕上がりのやさしさ・落ち着きから、さまざまな空間で活躍します。
🏠 家庭の壁面リノベーションに
リビングの一面だけを塗り替えるだけでも、部屋の雰囲気はガラリと変わります。
特に、家具や観葉植物との相性も良く、自然と暮らしになじみます。
🏡 古民家や中古物件のセルフリノベに
既存の壁紙の上から塗れる仕様なので、コストを抑えながら空間の“空気”を刷新できます。
木の柱や梁との相性も抜群です。
🏪 店舗・ギャラリー・アトリエなどに
空間の印象が直感的に伝わる場所では、CALMUR(カルミュール)の質感が大きな武器になります。
余計な装飾をせずとも、“雰囲気のある壁”が空間全体を引き締めてくれます。
CALMUR(カルミュール)は、ただの塗料ではなく、空間の表情を変えるための“ツール”です。
「自分の手で、心地よい空間をつくりたい」と思ったときに、最初に手に取ってほしい一缶。
塗装に慣れていない人こそ、一度試してみてほしいプロダクトです。
実際に塗ってみた!CALMUR(カルミュール)でつくる「わたしの壁」
「見た目は素敵だけど、実際に自分でも塗れるの?」
CALMUR(カルミュール)を知った読者の多くが、そう感じるはずです。
そこでここでは、CALMUR(カルミュール)を実際に使って壁を塗ってみた体験談として、塗装の流れや感想をリアルに紹介します。
作業の流れ|下地処理〜塗装〜仕上げまで
今回は、自宅リビングの一角。
白いクロス壁の一面(約6㎡)を、CALMUR(カルミュール)の「ライムストーン」という
ややくすんだグレーカラーで塗装してみました。
□ STEP1:準備と養生(約30分)
まずは家具を移動し、床やコンセント周り、天井との境界などにマスキングテープと養生シートを設置。
一見地味な工程ですが、これをしっかりやっておくと、後の仕上がりが格段に変わります。
CALMUR(カルミュール)は飛び散りにくい塗料ですが、念のため広めにカバー。
□ STEP2:下地チェックとプライマー塗布(約40分)
クロスの上からそのまま塗れる場合もありますが、今回は下地処理用のプライマー(推奨品)を使用。
ローラーで塗布し、約1時間ほど乾燥させました。ここでコーヒー休憩。
□ STEP3:CALMUR(カルミュール)塗装(1回目/約50分)
いよいよ本番。CALMUR(カルミュール)は最初、少し粘度が高く感じましたが、混ぜ棒でよくかき混ぜると滑らかに。
ローラーに取りすぎず、薄く薄く伸ばすように塗っていくのがコツ。
1回目は「ちょっとムラっぽい?」と感じましたが、焦らず乾かします。
□ STEP4:2回目塗装(約40分)
完全に乾いてから、2回目の塗装へ。
不思議なことに、2度塗りするとムラが自然に落ち着き、マットで均一な仕上がりに。
触ってみると、ざらっとした心地よい手触りと、少し光を吸い込むような質感。
✅ STEP5:養生を外して完成(約15分)
塗料が完全に乾いたのを確認してから養生を剥がします。
この瞬間、「おお、ちゃんと部屋が変わった」と感じる瞬間です。
約1日で施工完了。
作業時間・難易度・仕上がりのリアルな感想
全体の作業時間は、のべ約3.5時間(乾燥待ち時間除く)。
準備さえしっかりすれば、1日で仕上げられる作業です。
実際にやってみて感じたのは:
-
ローラーで塗るだけなので、想像以上にスムーズだった
-
漆喰“っぽさ”ではなく、しっかり「漆喰の雰囲気」がある
-
少しのムラや刷毛跡が、逆に味になるのがうれしい
-
失敗してもリカバーしやすい(乾いたらもう一度上塗りできる)
また、塗っている最中のにおいの少なさにも驚きました。
換気はしていましたが、作業中も作業後も「塗料くささ」はほとんど気にならず、ペットや子どもがいる家庭でも安心だと思います。
仕上がりの印象と、暮らしの変化
完成した壁を見てまず思ったのは、「空気が変わった」ということ。
白いクロスのときは無機質だった壁が、今では空間の“主役”になっているように感じます。
照明の光が柔らかく反射し、時間帯によって微妙に表情を変えるのも面白い。
家具や観葉植物との相性もよく、まるで空間全体が“呼吸している”ような感覚。
たった1面塗っただけなのに、「部屋に物語ができた」ような気がしました。
CALMUR(カルミュール)は、「ただ壁を塗る」のではなく、空間との関係性を変えてくれるプロダクトです。
自分で手を動かしたことで、部屋が“所有物”から“居場所”になった——そんな感覚が残りました。
まとめ|CALMUR(カルミュール)で、手の届く「理想の空間づくり」を
空間は、壁ひとつで変わります。
それは決して大げさな話ではなく、事実です。
今回紹介したCALMUR(カルミュール)は、“塗るだけ”で空間に呼吸を与えることができる漆喰塗料。
扱いやすく、デザイン性も高く、そして何より、「自分の手でできた」という実感を与えてくれるツールです。
塗装に自信がない人もいるでしょう。
不器用かもしれないし、途中で失敗するかもしれない。
それでも、自分の部屋に、自分の手をかけてみること。
その一歩は、きっとこれからの暮らしに、静かだけれど確かな変化をもたらしてくれます。
「やってみたい」を「できた」に変える一歩
DIYは、最初の一歩が一番むずかしい。
でも、CALMUR(カルミュール)のような“初心者を前提につくられた塗料”があれば、そのハードルはぐっと下がります。
-
仕上がりにこだわりたいけど、業者に頼むほどではない
-
自分らしい空間を、自分の手でつくってみたい
-
漆喰の風合いを、気軽に楽しんでみたい
そんな人にこそ、CALMUR(カルミュール)はぴったりです。
まずは、壁一面だけでもいい。
きっと、「こんなに雰囲気が変わるのか」と驚くはずです。
CALMUR(カルミュール)についてもっと知りたい方へ
「暮らしを、自分の手でつくる。」
その最初の道具として、CALMUR(カルミュール)がそっと寄り添える存在であれば、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。