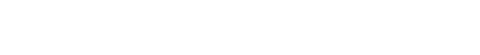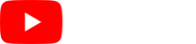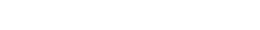ニュース
漆喰をあきらめたあなたへ──塗料で叶える空間づくり
コラム / 2025.06.24
漆喰(しっくい)と聞いて、まずどんなイメージが浮かぶだろうか。
白く、しっとりとした質感の壁。空間の湿度を整え、静かに呼吸するような佇まい。
自然素材ならではのぬくもりや落ち着きがあり、
長く使い込むほどに味わいが増していく。
そんな漆喰の存在感に、魅力や憧れを感じている人は少なくないだろう。
実際、漆喰は長い年月をかけて建築に使われてきた素材だ。
古民家、茶室、蔵、そして現代の和モダン住宅に至るまで、さまざまな空間を彩ってきた。
その美しさと、素材としての力強さは、プロ・アマ問わず広く支持されている。
しかし一方で、その魅力を知れば知るほど、現実との距離も感じやすい。
「自分では扱えない」「左官職人にしかできない」「コストがかかる」「工期が読めない」。
漆喰は手間も技術もかかるという印象が強く、実際に採用に踏み切れない──
そんなジレンマを抱えているDIYユーザーや設計者、工務店、施主は多いはずだ。
ところが近年、この状況に変化が起きている。
従来の左官仕上げによらず、ローラーや刷毛で塗れる漆喰塗料が
登場し、注目を集めているのだ。

“漆喰風”ではない。本物の漆喰の成分を活かしながら、施工性を高めた「漆喰塗料」
下地処理が比較的シンプルで、道具も特殊なものはいらない。
それでいて、質感や性能は左官材にも引けを取らないレベルにまで進化している。
このように、漆喰はもはや「職人だけのもの」ではなくなりつつある。
漆喰という素材に込められた思想や機能性はそのままに、
“誰でも扱える形”へと開かれてきた。これは単なる簡易化や省力化の話ではない。
漆喰の価値そのものを、もっと多くの人に届けられる時代が来たということだ。
この記事では、そんな漆喰塗料という存在をあらためて掘り下げていく。
なぜ今、漆喰塗料が注目されているのか。従来の漆喰と何が違い、何が同じなのか。
そして、左官ではない手法で漆喰を取り入れるという選択肢が、なぜ意味のあることなのか。
素材を諦めるのではなく、素材とつながり直すための手段として。
漆喰塗料は、ただ便利な代用品ではなく、“新しい本物”として語る価値がある。
それを感じてもらえる内容を、ここから丁寧に紐解いていきたい。
1. 漆喰という素材の魅力とハードル
漆喰が長年にわたって支持されてきた理由は、その表面的な美しさだけでなく、
素材としての本質的な魅力にある。
石灰を主成分とする漆喰は、自然素材でありながらさまざまな機能を持っている。
調湿性、消臭性、防カビ性、耐火性…。
いわば、呼吸する壁として、空気を整え、住まいの環境を守ってくれる存在だ。
それでいて、見た目も美しい。
職人の手で丁寧に塗られた漆喰の壁は、均一な中にもわずかな揺らぎがあり、
光を柔らかく受け止めるマットな質感が空間全体に静けさと深みを与えてくれる。
漆喰が使われている空間には、どこか安心感がある。それは、素材の性能だけでなく、
人の手でつくられたという空気感によるものだろう。

こうした特徴から、漆喰は自然素材を好む住宅・店舗・施設などで人気が高く、
古民家や和風建築だけでなく、カフェ、美容室、子ども部屋などにも幅広く取り入れられている。
しかし、これほど魅力にあふれた素材でありながら、導入には常にハードルがつきまとう。
まず第一に挙げられるのが、施工の難しさだ。
漆喰を塗るには、材料の練り方、塗る厚み、乾燥の見極め、仕上げの均し方など、
細かな技術が求められる。しかもその技術は、長年の経験に裏打ちされた職人の“手”によるものだ。
仕上がりは職人の腕に左右されやすく、クオリティの安定も簡単ではない。
だからこそ美しいが、だからこそ扱いづらいというジレンマがある。
さらに、コストの問題も大きい。材料費だけでなく、
手間賃・工期・人員の確保など、左官工事にはさまざまな要素が絡む。
予算が限られた現場では、どうしても「漆喰はいいけど、難しいよね」と見送られがちだ。
そして、DIYで扱うには難易度が高すぎるという現実。
SNSや動画で見るような漆喰仕上げに挑戦してみたくても、調べれば調べるほど「無理かも」と感じてしまう。
結果として、漆喰の魅力を知っていても、現実的な選択肢からは外れてしまう。
「気にはなるけど手が届かない」「いいけど無理だよね」──
そんな声が、漆喰のまわりには今も多く存在している。
それは、素材のせいではない。むしろ、漆喰が優れた素材である証でもある。
ただ、扱える人が限られているがゆえに、選択肢になりにくい。
この構造そのものが、これまで漆喰を遠ざけてきた背景にあるのだ。
2. 技術の進化と漆喰塗料という選択肢の登場
漆喰の施工が難しく、限られた人しか扱えなかった背景には、
「素材に合わせて、人が寄り添うしかなかった」という事情がある。
でも、建材や塗料の分野は常に進化を続けている。
そしてここ数年、その技術進化が漆喰の世界にも静かに、しかし確実に波及している。
従来、漆喰を使いたければ左官職人に依頼するしかなかった。
また、自分で何とかしようと考えたときに出てくる選択肢といえば、
漆喰風クロスや漆喰風ペイント──つまり“似せた素材”がほとんどだった。
見た目はなんとなくそれっぽい。けれど、手触りや空気感はまったくの別物。
本物を知る人には「漆喰風」という言葉がすでに物足りなさを含んでいた。
そんな中で登場したのが、本物の成分を含んだ「漆喰塗料」という存在だ。

漆喰塗料は、従来の左官材と同様に石灰をベースにしながらも、
ローラーや刷毛など、一般的な塗料の道具で施工できるように調整された塗料。
仕上がりは“漆喰風”ではなく、「ちゃんと漆喰らしい」ことを目指してつくられている。
扱いやすさだけを追求したのではなく、機能性も妥協していない。
調湿性や防カビ性、消臭性など、漆喰本来の特性を持ちつつ、施工性をぐっと引き下げた。
さらに、左官ほど高度な下地処理が必要ない製品も多く、
乾燥時間や施工環境に対する制約も比較的ゆるやか。
工期の短縮や人員調整が求められる現場にとっても、現実的な選択肢になり得る。
重要なのは、これは“なんちゃって素材”ではないということ。
左官とは違うルートから、漆喰という素材にアプローチしている別の技術なのだ。
つまり、漆喰塗料の登場は、「漆喰を使いたいけれど諦めていた人たち」に向けて、新しい入り口を用意してくれた存在だと言える。
そしてこの入り口は、単なる簡略化ではなく、素材の魅力をもっと広く伝えるために生まれた“進化”なのだ。
3. “なんちゃって”じゃない。職人も納得するクオリティ
漆喰塗料と聞いて、最初に思い浮かぶのは「本当に漆喰と同じなのか?」という疑問だろう。そう思うのも無理はない。
これまでも「漆喰風」と名のつく製品は数多く出回っていたし、中には見た目だけ似せた薄い塗膜のような商品もあった。
だが、現在の漆喰塗料の中には、その疑念をいい意味で裏切るものがある。

たとえば質感。あの漆喰特有の、少し粉を吹いたような乾いたマットな表情。
光の反射が控えめで、壁が空間の一部として静かに呼吸しているような質感。
本来、左官によってしか出せないとされてきたこの雰囲気を、
漆喰塗料でほぼ再現できてしまう──そんな製品も登場している。
さらに、調湿性や防カビ性、消臭性といった機能面でも、
石灰成分をしっかり含んでいる塗料であれば、従来の漆喰に匹敵するレベルを実現している。
一部の製品では、原材料の消石灰比率や顔料の選定にまでこだわり、
左官職人が見ても「これ、塗料なの?」と驚くほどの仕上がりになることもある。
特に注目すべきは、プロの職人が実際に使い始めているという事実だ。
左官職人にとっては、自分の手でコテを握り、塗り上げること自体が仕事であり誇りだ。
だからこそ、“漆喰を塗る”という行為に強いこだわりを持っている。
そんな彼らの中にも、「この仕上がりなら現場に使える」と評価する人が出てきている。
質感、作業性、再現度──塗料であっても“漆喰として成立している”と感じられるレベルに達しているからだ。
もちろん、すべての漆喰塗料が同じではない。
中には漆喰成分がごくわずかで、実質アクリル系塗料に近いものもある。
だからこそ、成分や特徴を理解し、見極めて使う視点が求められる。
だが確実に言えるのは、「左官じゃないと出せない味」と思われていた漆喰の世界に、
塗料という別のアプローチから、しっかりと食い込める製品が存在しているということ。
これは単なる便利さではない。
プロの目にも耐える「もう一つの漆喰」が、今、形になっている。
4. 使い手が広がることで起きる変化
漆喰塗料の本当のインパクトは、
“質感を再現できる”ことだけではなく、「誰が使えるか」が変わったことにある。
漆喰の施工ができる人は限られている。
でも、漆喰塗料なら、その可能性をもっと広げられる。
たとえば、DIYユーザー。
これまで、漆喰は「自分でやるにはハードルが高い素材」の代表格だった。
練り方、塗り方、乾燥時間、下地処理…どれをとっても技術と経験が求められ、
「興味はあるけど、やめておこう」と諦めた人も多かった。
でも、ローラーや刷毛で扱える漆喰塗料であれば、話は変わる。
下地さえ整っていれば、一般的なペイント感覚で施工ができる。
それでも質感はしっかり漆喰。仕上がりの満足度が高い。
「自分の手で仕上げた空間に、本物の素材感がある」という喜びは、
DIYの醍醐味として大きな価値になる。

一方で、工務店や設計者にとっても、漆喰塗料の存在は提案の幅を広げてくれる。
左官に頼らなくても、漆喰のある空間を実現できる──
それは、予算やスケジュールの都合で泣く泣く見送っていた提案を、再び実現できるチャンスでもある。
そして、塗装職人にとっては新しい領域の拡張だ。
これまで「漆喰=左官の仕事」と分業されていた領域に、
塗装としてのアプローチで入り込めるようになった。
また、左官職人にとっても「下地だけ」「仕上げだけ」「部分的に塗料で補完」といった
ハイブリッドな施工提案がしやすくなる。
こうした“使い手の拡大”は、素材の定着を加速させる。
知っている人、使える人、触れる人が増えることで、
漆喰はますます「現実的な選択肢」として社会に浸透していく。
そしてそのきっかけをつくっているのが、漆喰塗料という現代的なアプローチなのだ。
5. CALMUR(カルミュール)という具体的な提案
ここまで漆喰塗料の背景と可能性について掘り下げてきたが、
実際にどんな製品があるのか、気になってきた人もいるだろう。
その代表例として紹介したいのが、CALMUR(カルミュール)だ。

CALMUR(カルミュール)は、伝統的な漆喰の美しさと性能をベースにしながら、
現代の住空間や施工現場のニーズに応える形で開発された漆喰塗料。
主成分はもちろん消石灰。本物の漆喰に欠かせない成分をきちんと含んでいる。
防カビ性・調湿性・脱臭性といった、漆喰が本来持っている機能はそのままに、
ローラーや刷毛で塗れる施工性が備わっているのが最大の特長だ。
そして、CALMUR(カルミュール)を語る上で欠かせないのが、質感のリアルさである。
塗料でありながら、仕上がりは驚くほどナチュラル。
粉っぽく、マットで、光を吸収するような柔らかい表情。
まるで左官仕上げのような、品のある静けさが壁一面に広がる。
「これ、塗料なんですか?」と驚かれることも少なくない。
さらに、天然鉱物顔料による色彩表現も魅力だ。
柔らかいニュアンスのある色味が多く、いかにも“塗りました”という感じが出にくい。
ナチュラルで空間になじみやすく、どんなインテリアにも調和する。
加えて、CALMUR(カルミュール)は施工の自由度も高い。
ローラーや刷毛だけでなく、コテやスポンジなどを使って表情をつけることもできる。
“素材を楽しみながら仕上げる”という醍醐味を、プロ・DIY問わず味わうことができるのだ。
たとえばDIYユーザーがCALMUR(カルミュール)を使えば、
「自分の手で、本物の漆喰の質感に近い空間をつくった」という体験になる。
職人が使えば、「短工期で安定した漆喰質感を出せるツール」として、現場の武器になる。
コスト面でも、CALMUR(カルミュール)は左官による漆喰施工に比べて導入しやすい価格帯に設定されている。
「漆喰は高いから…」と諦めていた人にとって、再考のきっかけになる可能性がある。
もちろん、すべてをCALMUR(カルミュール)で代替できるわけではない。
左官による手仕事の魅力は唯一無二だし、施工環境によっては適材適所の判断が必要になる。
だが、CALMUR(カルミュール)のように、漆喰の“本物らしさ”を残したまま施工の自由度を広げた製品があることは、
素材選びにおける視野をぐっと広げてくれるはずだ。
これは“妥協”ではない。むしろ、現代に合ったかたちで漆喰を再解釈した結果としての一つの完成形。
漆喰を使いたいすべての人にとって、CALMUR(カルミュール)は
その思いに応えるリアルな選択肢になる。
6. 選択肢を持つことの価値

漆喰塗料という選択肢が広がってきた今、
私たちが改めて見直すべきなのは、「選べること」そのものの価値かもしれない。
漆喰を使いたい──
そう思ったときに、以前は「左官に頼むしかない」「高い」「難しい」という理由で諦めざるを得なかった。
気に入っていても、現実的には選べない素材。それが漆喰だった。
でも今は違う。
CALMUR(カルミュール)のような製品が登場し、漆喰を塗料として扱えるようになった今、
その“あきらめ”に代わる選択肢が、私たちの手の届く場所にある。
ここで大切なのは、漆喰塗料を「漆喰の代用品」として見るのではなく、
「漆喰を別の方法で実現する技術」として捉えることだ。
左官を否定するわけではないし、簡単なほうが正しいとも限らない。
ただ、現場や人、それぞれの事情に応じて、選べる手段が増えるということ。
それが、住まいや空間づくりにおいてどれほど大きな自由をもたらすかは言うまでもない。
妥協ではなく、解釈。
省略ではなく、選択。
そして、素材に敬意を払いながらも、扱いやすさを求めるという視点があるからこそ、
漆喰塗料という新しい形は「誠実な進化」として評価できる。
知らなければ、選べない。
選べなければ、可能性は生まれない。
CALMUR(カルミュール)のような製品があることを知っていれば、
「漆喰を使いたい」と思ったときの選択肢は、確実に増えている。
選べるということは、自分の理想に少しでも近づけるということだ。
それは、ものづくりにおいてとても力強いことだと思う。
7. CALMUR(カルミュール)の活用シーンと広がる可能性
CALMUR(カルミュール)のような漆喰塗料は、その使いやすさと質感の両立によって、
さまざまな空間で柔軟に活かされている。
ここでは、実際に活用されているシーンや、相性のよい空間の例をいくつか紹介しておきたい。

まず代表的なのが、個人住宅のリビングや寝室。
住まいにおいて、壁が占める面積は非常に大きい。
そこにCALMURを使うことで、空間全体の雰囲気が大きく変わる。
光の反射が柔らかく抑えられ、質感のある壁が目に入るたびに、心が静まるような感覚がある。
特に木材や自然素材と組み合わせると、素材の良さを引き立て合うような調和が生まれる。
次に、子ども部屋や寝室などのプライベート空間。
CALMURは原材料に石灰を使っており、VOC(揮発性有機化合物)が極めて少ない。
そのため、室内空気の質を重視したい空間にも安心して使える。
また、調湿性や防カビ性もあるため、湿度がこもりがちな部屋にも効果的だ。

店舗やオフィス空間にもCALMURは向いている。
例えば、カフェやアパレルショップなど、「空間の雰囲気」そのものがブランド価値と直結する場所では、
壁の素材感が印象を大きく左右する。CALMURなら、ナチュラルで落ち着いた印象を演出しながら、
施工も比較的スピーディーに行える。設計者にとっては、質感と現実性のバランスが取れる便利な素材だ。
また、最近増えているのが小規模リノベーションでの活用。
DIYユーザーが賃貸や中古住宅の一部を自分で改装するケースも増えており、
「ちょっと壁を変えてみたい」というときに、CALMURはちょうどいい選択肢になる。
さらに、施設や公共空間など、不特定多数の人が出入りする場所でも、
落ち着きのある空間演出と環境性能を両立したい場合にはCALMURの特性が活きる。
カビや匂いに配慮したい医療施設や福祉施設でも、検討に値する素材だ。
このように、CALMURは「DIYでちょっと試す」から「商業空間の本格仕上げ」まで、
さまざまなスケールと目的にフィットする柔軟性を持っている。
その懐の深さこそが、“現代的な漆喰”としてのCALMURの強みなのかもしれない。
8. まとめ
漆喰は長い歴史の中で、職人の手によって丁寧に扱われ、
美しさと機能性を兼ね備えた素材として重宝されてきた。
その価値は、今もまったく揺らいでいない。
しかしその一方で、「憧れるけど使えない」「いい素材だけど、現実的ではない」──
そう感じてしまう人が多かったのも事実だ。
そんな中で登場した漆喰塗料、そしてCALMUR(カルミュール)は、
漆喰の価値を損なうことなく、もっと自由に、もっと広く使える形を提示してくれている。
DIYユーザーにとっては、「憧れの素材を自分の手で仕上げる」喜びを。
設計者や工務店にとっては、「現実的に提案できる漆喰空間」を。
職人にとっては、「仕事の幅を広げる新しいアプローチ」を。
CALMUR(カルミュール)は、誰かの憧れやこだわりを、現実の空間へ落とし込むための“きっかけ”になる存在だ。
素材は選ばれることで生きる。
そして、選べる幅が広がることは、素材の未来を明るくする。
漆喰塗料は、漆喰を諦める手段ではない。
むしろ、もう一度素材と向き合うための、今の時代なりの答えかもしれない。
漆喰に興味があるなら、CALMUR(カルミュール)という手段を、ぜひ一度選択肢に入れてみてほしい。
それは、あなたの空間づくりにとっても、きっとポジティブな一歩になるはずだ。